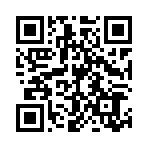2012年02月06日
「コーチングで、子育ても仕事もばっちり!」
おはようございます。栗が丘クリニック マネージャーの荒井です。
最近、「コーチング」という言葉が一般に少しずつ浸透してきた感がありますが、あなたはいかがお感じでしょうか?
子育てはもちろんのこと、最近では会社組織でもコーチングの手法を取り入れているところが多くなってきているようです。
さて、そもそも「コーチングとは何ぞや?」ということになるのですが、ネットの検索サイト「ウィキペディア」によると、「コーチングとは、人材開発のための技法のひとつ。「コーチ」(COACH)とは馬車を意味し、馬車が人を目的地に運ぶところから、転じて「コーチングを受ける人(クライアント)を目標達成に導く人」を指すようになった。よく知られたところではスポーツ選手の指導があるが、現在では交流分析や神経言語プログラミング(NLP)などの手法を取り入れてビジネスや個人の目標達成の援助にも応用されている、と出ています。
では、「なぜ今、コーチング」がもてはやされるようになってきたのでしょうか?
その理由を会社組織に見て行きたいと思います。
その最大の理由は、それまで主流だった「コンサルティングの手法が世の中に通用しなくなってきたから」です。
コーチングとコンサルティングの最大の違いは「目標に対する自主性」にあります。
これは、いつもお話させていただいている「want to」か「have to」か、ということに繋がります。
つまり、「自ら“それ”をやりたい(want to)かやりたくない(have to)か?」という言葉に集約されるのです。
コンサルティングを行う「コンサルタント」の役割は、「多くの一般人が気づいていない『世の中の未来の流れ』を的確に読んで、何らかの目標を指し示す」ことです。
これは、本当の意味でのクライアント(従業員)から見れば「何らかの目標を課せられている」=「have to」の世界観に位置していることになります。
また、今ほどお伝えさせていただきましたとおり、本当の意味でのクライアントとクライアント(コンサルティングを依頼した張本人=社長等の経営陣)が全くの別人であることにも大きな問題が潜んでいるのです。
潜在的に誰もが気づいているとおり、これは「世界中にありとあらゆるモノやサービスが溢れてしまったために『誰もが欲しいモノやサービス』がなくなってしまった」=「比較的、目に見えやすく、わかりやすい指標がなくなった」ことと、さらに世の中の成長・変化するスピードがものすごく速くなったことで、「押し付けようとした価値観」=コンサルティングが通用しなくなってきていることを示しているのです。
つまり、右肩上がりの経済成長が一斉に止まったために「『何を、どうして良いのか?』が分からなくなった」=「ニーズが多種多様になり、民衆の価値観をある程度『ひとくくり』にすることが難しくなった」=「扇動が難しくなった」ことを証明しているのです。
まだまだ潜在意識のレベルではあるものの、経営者も従業員もこれまで信じ込んできた(信じ込まされてきた)価値観=「会社の在り方」や「働き方」「働く意義」について確実に違和感を抱くようになってきている、それが会社でコーチングが採用されてきている本当の理由なのです。
あなたの会社のコーチングに対する認識や動きはいかがでしょうか?
ということで、本日もお読みくださいましてありがとうございました。
クリニック携帯サイトhttp://katy.jp/kurigaoka-clinic/(PCからもご覧いただけますし、PCからメルマガ登録もできます!)
配信停止ご希望の方は、次のアドレスまで空メールをお送りください→stop_kurigaoka-clinic@katy.jp
最近、「コーチング」という言葉が一般に少しずつ浸透してきた感がありますが、あなたはいかがお感じでしょうか?
子育てはもちろんのこと、最近では会社組織でもコーチングの手法を取り入れているところが多くなってきているようです。
さて、そもそも「コーチングとは何ぞや?」ということになるのですが、ネットの検索サイト「ウィキペディア」によると、「コーチングとは、人材開発のための技法のひとつ。「コーチ」(COACH)とは馬車を意味し、馬車が人を目的地に運ぶところから、転じて「コーチングを受ける人(クライアント)を目標達成に導く人」を指すようになった。よく知られたところではスポーツ選手の指導があるが、現在では交流分析や神経言語プログラミング(NLP)などの手法を取り入れてビジネスや個人の目標達成の援助にも応用されている、と出ています。
では、「なぜ今、コーチング」がもてはやされるようになってきたのでしょうか?
その理由を会社組織に見て行きたいと思います。
その最大の理由は、それまで主流だった「コンサルティングの手法が世の中に通用しなくなってきたから」です。
コーチングとコンサルティングの最大の違いは「目標に対する自主性」にあります。
これは、いつもお話させていただいている「want to」か「have to」か、ということに繋がります。
つまり、「自ら“それ”をやりたい(want to)かやりたくない(have to)か?」という言葉に集約されるのです。
コンサルティングを行う「コンサルタント」の役割は、「多くの一般人が気づいていない『世の中の未来の流れ』を的確に読んで、何らかの目標を指し示す」ことです。
これは、本当の意味でのクライアント(従業員)から見れば「何らかの目標を課せられている」=「have to」の世界観に位置していることになります。
また、今ほどお伝えさせていただきましたとおり、本当の意味でのクライアントとクライアント(コンサルティングを依頼した張本人=社長等の経営陣)が全くの別人であることにも大きな問題が潜んでいるのです。
潜在的に誰もが気づいているとおり、これは「世界中にありとあらゆるモノやサービスが溢れてしまったために『誰もが欲しいモノやサービス』がなくなってしまった」=「比較的、目に見えやすく、わかりやすい指標がなくなった」ことと、さらに世の中の成長・変化するスピードがものすごく速くなったことで、「押し付けようとした価値観」=コンサルティングが通用しなくなってきていることを示しているのです。
つまり、右肩上がりの経済成長が一斉に止まったために「『何を、どうして良いのか?』が分からなくなった」=「ニーズが多種多様になり、民衆の価値観をある程度『ひとくくり』にすることが難しくなった」=「扇動が難しくなった」ことを証明しているのです。
まだまだ潜在意識のレベルではあるものの、経営者も従業員もこれまで信じ込んできた(信じ込まされてきた)価値観=「会社の在り方」や「働き方」「働く意義」について確実に違和感を抱くようになってきている、それが会社でコーチングが採用されてきている本当の理由なのです。
あなたの会社のコーチングに対する認識や動きはいかがでしょうか?
ということで、本日もお読みくださいましてありがとうございました。
クリニック携帯サイトhttp://katy.jp/kurigaoka-clinic/(PCからもご覧いただけますし、PCからメルマガ登録もできます!)
配信停止ご希望の方は、次のアドレスまで空メールをお送りください→stop_kurigaoka-clinic@katy.jp